こころざし課題図書(平成22年5月度)
2011年2月23日 07:30
“こころざし”平成22年5月分課題レポートは、世界を知る力 / 寺島 実郎 著でした。 その時に提出した私のレポートを以下に掲載します。
1.自らを相対化し客観化する
私達が、これまで学んできた事は、この事に尽きるのではないか。工業振興ビジョンを作成する過程で、「地域を活性化させないといけない事はよくわかるが、経済環境が大変厳しい時に、自社も自分もとても忙しいし、それどころではない」、という声がよく聞かれた。
しかし、この考え方は余りにも狭い考え方と言わざるをえない。自社のビジョンを考える時に、客観的にみて自社はどういう存在なのか? 地域がどうあれば、そこで事業を営む企業が活性化するのか?という視点がなければ、長期的に見て自社の戦略も的外れの物になる危険性がある。
時代をどう捉えるのか? そして、自社はどういう役割を果たすのか?を、鳥瞰図(大局観測)と虫験図(現場の臨場感の中での思考)の視点でしっかりとらえることが大切である事を改めて感じる。
私達は、“こころざし”での2年間よく学んできたと思う。多くの講師の先生方の話を聴き、議論を重ね、アドバイザーの方に考え方を学び、毎月しっかりレポートを提出した。
しかし、この会が他の経営者の勉強会とどこが違う? 客観的に見て、より広い視野で地域の事を捉え、長期的な視野で自社の戦略を考え、そして実践できているか? 次世代リーダーとしての自覚を持っているか? 自分に何ができる? 自分に何が求められている? 自問自答を繰り返す必要があると思う。当事者意識をもって、地域のあり方に関わり、行動をしていくべき時だ。 勉強は十分やった。さあ、どう行動に結び付けよう?
2.分散型ネットワーク革命
世界が「多極化」するなかで、ネットワークを形成できる国や地域だけが力を発揮できる時代へかわると、著者はいう。大規模・集中型の文明体系から、分散型ネット社会への転換が行われるという。
大企業中心の傾斜生産方式による産業復興は非常に効率がよかった。中小企業もその仕組みの中に組み込まれていた。仕事は営業しなくても頂ける仕組みだった。しかし、成熟した社会では、多様化した需要への対応が必要となってくる。 ヨーロッパの小企業憲章をみてもわかるように、EUはグローバリゼーションや加速する技術革新に挑戦する中小企業の成長と潜在的な改革能力が期待されている。
ドラッカーの唱える知識主体の経済では、多様な中小企業の網の目のように張り巡らされたネットワークによるハイレベルな連携によって競争力のあるダイナミックな経済が生まれるとされている。
「分散型ネットワーク」社会へのパラダイム転換は、日本の可能性を拓くと著者もいっている。日本のいたるところで連携組織が生まれている。 私達も当地域を拠点に、さまざまな地域と有機的なネットワークを構築していくべきだと思う。
3.ものづくりへのこだわり
日本が誇りうるものは、「ものづくりへのこだわり」と「技術への敬愛」であり、「分散型ネットワークの時代」に照準をあわせて、技術を育て、事業を育てる、「育てる資本主義」こそ、日本の歩むべき道があるという著者の言葉に大いに勇気づけられた。
以上
やはり、ネットワーク作りをしないといけないときだと思います。宮崎でも産学官が連携して、地域産業の活性化のために、今年は、ネットワーク組織を作っていきたいと思っています。
以上です。
社員への手紙 その24
2011年2月22日 07:00
今回は、平成15年9月1日に書いた9月度の手紙です。
拝啓
今年は冷夏で雨の多い夏でしたが、ここのところ遅れてきた夏のようです。残暑が続くようですが、夏ばてなどないよう体調には十分お気を付けください。
今年もまた、8月30日(土)に皆さんと共に夏祭りを開催することができました。ご協力ありがとうございました。夏祭りも3回目を迎え、みんなで作る年1回のイベントとしても定着してきました。
今年は盆工事を60人体制で行ったため8月中は非常に忙しく、当初の予定から延期しての開催でした。準備期間としては、たったの1週間しかありませんでしたが、協力し合い、素晴らしい夏祭りを開催することができました。
過去2年間の経験があったということも有り、準備に協力頂いた方々からは、いろいろな意見を出して頂きながら、すすんでそれぞれの役割を果たしてくれました。
皆さんの本気での取り組みが大きな力となるということを改めて感じます。ありがとうございました。
ご家族の皆さんも多数ご参加頂き、ありがとうございました。夏休みの最後の土曜日を共に楽しく過ごすことができました。今後ともご苦労をおかけすることもあるかと思いますが、ご支援頂きたく、お願い申し上げます。
我が社は、創業以来お客様の工場の安定した操業を支えるために、突発のメンテナンスや長期休暇中の設備工事を主体に仕事を行ってまいりました。そのため、ご家族への負担も大きかったかと思います。
しかし、そのおかげでお客様からかわいがって頂き、この厳しい時期に継続して仕事も頂くことが出来ています。また、どういう仕事もいとわず取り組んできたおかげで技術力も養われてきました。
いまどの業界も厳しくなり、24時間365日のサービスが当たり前になってきましたが、いつでも、どこでも、協力できる体制が実際組めている企業は少ないと思います。様々な形でお客様のご要望に応えていかなくてはいけません。
「企業は、環境適応業である」といわれます。会社の事業にも事業環境にもサイクルがあり、いい時もあれば悪いときもあります。環境の変化に即していくことが大事です。悪いときに、それに対する努力をした企業が新しい変化に対応した体質に変化することができるはずです。
10月1日をもって、日向中島鉄工所とユウ・エス・シーを合併し、新しい体制で来期に臨みます。事務作業が効率化されると共に、合併することで全社一丸となって難局に取り組む体制をつくりたいと考えています。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
敬具
我が社は、機械を作るだけでなく、設置や設備工事も行っていますので、一年を通して、休日の日にも仕事が入ります。 いかに、うまく調整をしながら、休みをつくり、会社全体の行事を作るかに頭を悩ませます。 いま、夏まつりも中止していますが、また出来るようになるといいな。
以上です。
致知の記事から(2011年3月号)
2011年2月21日 06:00
月刊誌「致知」の3月号の記事のなかから、紹介します。
スポーツドクターの辻秀一さんの「ツキを生むフロー理論」からです。
フロー理論とは、スポーツ心理学でいわれる「ZONE」の概念に近いかもしれない。外部環境に関係なく、その状況に即した最幸のパフォーマンスが発揮できる心の状態を指す。いわば“揺らがず・とらわれず”という精神状態で、常に機嫌のよい感じとでもいえばよいだろうか。
「揺らぐ」とは、うざいとか、むかつく、がっかりや不安といった、感情が揺れ動いている状態。
「とらわれる」は、過去の経験に基づいて脳が勝手に意味づけをし、思い込みを創り出している状態。会社で社長が何かをやるぞと言っても、社員の方が「無理です」と口にすると、その言葉にとらわれて実現は難しくなる。
最大の敵は、相手ではなく、自分の中にあるとらわれ。また目標へ向かう間に揺らぎが生じると、そこへは到達しにくくなる。“揺らがず・とらわれず”でいれば、自分が行きたいところへちゃんといけるのに、それをさせない理由を創り出すことに脳は長けている。
それが「認知」の脳である。そのために、多くの人は、できない事の理由探しをし、何かしらの意味づけをしているのである。
そうした従来の生き方からの脱却をしていくために重要なのが、自分自身の心の状態だ。
実際にフロー状態を創り出すにはどうすればいいのか?
第1は、自分の心の状態に気付く力を付ける事。
第2は、フローで売ることの価値を認識する事。
第3は、なぜ、人間はノンフローになってしまうのかをいう仕組みを良く理解させる事。
心の状態をフローに傾かせるための4大ツールがある。それが、「表情、態度、言葉、思考」である。
心をフロー化する考え方には、次のようなものがある。
「好きなことを考える」、「いまに生きる」、「一生懸命やる」、「感謝する」、「リスペクトする」、「信じる」
世の中で成功者と言われる人とそうでない人の差も、外部環境に左右されず、安定したパフォーマンスを常に発揮できているかどうかにあると言えるだろう。
つまり結果だけでなく、すべてのプロセスにフローを伴いながら生きている人が、成功もてに入れやすく、日々を充実して生きる事ができる。そして、結果のみが成功でないとわかっている人が、最終的に結果の成功も手に入れているのである。
“揺らがず・とらわれず”の状態になると、自然に発揮される人間固有の二つのスキルがある。一つは成長するスキル、もうひとつは愛するスキル。
フロー化が起こると、この成長と愛のスキルが強化され、高いパフォーマンスへの結びつく、その結果、人間関係がよくなり、思いがけないものが手に入るようになったりするために、運やツキが出てきたように思える。
一秒一秒、一瞬一瞬の姿勢を私たちは絶えず問われており、そのあり方が人生を決めていくのである。
いつもフローの状態でいるために、粘り強く、繰り返し、心の状態を意識していこうと思います。
本日は、以上です。
自分史(その22)、エジプトその2
2011年2月20日 07:12
やっと、エジプトではデモがおさまりました。 でも暴動やクーデターでしか、政権が交代しないというのも、イメージが悪いですね。 敬虔なイスラム教信者や労働者クラスの方は、真面目な方が多いのに、残念です。
エジプトでは、カイロの南、マーディーという町で、フラット(アパート)を借りて、共同生活をしていました。 この町は、アメリカ人が開発をしたという土地柄で、閑静な住宅地という感じでした。 近くにはスポーツクラブもあり、テニスやプールもありました。
大体フラットは、お医者さんなどの地位の高い人が経営をしています。 私たちのフラットもMr.トッソンと言う方の持ちモノでした。 入口には、バーバーという門番のおじいさんがいつも座っていました。
運転手つきの車を契約していました。 運転手は、Mr.サイードと言いました。 プロの運転手です。 何もない時は、ゆったりと運転をしているのに、時間がない!というと、すっとばしてくれました。職務に忠実な運転手です。 日本食(もどき)のコックも雇っていました。名前はなんだったかな? 日本食っぽい食事を作ってくれました。 お米は、現地での調達で、あまり質の良いものではありませんでした。 石や虫の糞?みたいなものも交じっていて、コックが一つ一つより分けていました。
料理の得意な上司がいて(前掲の厳しい上司、田所さん)、時々、エビのてんぷらを作ってくれました。 この海老が最高だったのを覚えています。 揚げたてを塩で食べるのってこんなにおいしいの、って思いました。
休みの日には、車で北へ30分のカイロ町中までいっていました。いろいろなホテルの朝食バイキングを食べたり、日本食レストランの寿司(もどき?)を食べたりする事が楽しみの一つでした。 シャリがベチャットして、ネタは新鮮でなくても、雰囲気を楽しんでいたのかな?
また、2週間の休みを終えてもどってくる赴任者がいると、携行可能重量ぎりぎりの食料を運んで来てくれていました。 とっても楽しみにしていました。 その中でも定番が棒ラーメンです。休日の朝食に棒ラーメンを自分達で作って食べるのも、休みの風景になっていました。
今日はここまで、です。
マラソン大会
2011年2月19日 07:30
実は、私は、健康オタク(?)です。 家を作る時には、真剣にトレーニングルームを作ろうかと考えたくらいです。 昔から、体を鍛える事や、健康に関する事がとても好きで、色々なことを試してきました。 我が家には、通販で買った健康器具がたくさんあります。 鉄アレイはもちろん、ヨガマットや傾斜板、レッグマジック、ウイーフィット、なんと高下駄まであります。
スポーツをする時に、体力不足で息切れして、スポーツ自体を楽しめないのが、いやで、昔から、筋トレやジョギングを好んでしていました。
昔は、会社の昼休みに、約3キロのコースを本気で走っていました。1キロ3分台を目標に毎日汗だくになっていました。
それが高じて、いろいろなマラソン大会にも、出場していました。宇部健康マラソン、相生マラソン、防府マラソン、ホノルルマラソン、宮崎青島太平洋マラソン、綾照葉樹マラソン、日向ひょっとこマラソン、シーガイアトライアスロンなどなど。
それぞれのマラソンの話は、また別の機会に報告しますが、今日はこれからの話です。
マラソンを走ることで、ガンを克服した方がいます。 杉浦貴之さんです。今年のホノルルマラソンもガンの方々と一緒に走った方です。
ことしの西都原このはなマラソン(3月20日(日))に参加をされるので、私たちも一緒に走ろうといっています。 久々のマラソンなので、完走できるか、不安も少々ありますが、仲間と一緒に楽しんで走ろうと思います。
杉浦貴之さんからのメッセージです。
「11年前、ぼくは病院のベットで、『ホノルルマラソンに出たい!』という夢を抱きました。ゴールシーンを思い浮かべては実際に涙するほどのありありと描き、辛い治療を耐え抜きました。トイレに行くのも辛かった時、その一歩一歩のゴールが便器ではなく、ホノルルのゴールだと連想できた時、その復活の一歩一歩が本当に力強いものになりました。
手術から6年後の2005年、その夢がかないます。そのとき、僕が発した言葉は、
『走れるほどに元気になったのではなく、走ったから元気になりました!』
僕の生きがいは、宝物のおすそわけ。『走って元気になる』この事を沢山の人に体感して欲しくて、2010年12月は、自分一人ではなく、がんサバイバー(患者さん、経験者)、ご家族、サポーターでチームを作り、80人以上の仲間でホノルルマラソンに参加します。
ホノルルのゴールで80人以上の夢がきらめきます。そして、2011年3月は、宮崎県西都市です! トーク&ライブは、口蹄疫復興チャリティーとなっています。宮崎に来てもらうだけで、支援になりますので、全国のみなさん、ぜひぜひ、お越しください。僕を元気にしてくれた宮崎のパワーを体感してくださいね。」
以上です。



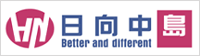

最近のコメント