夢を語ろう! トークライブin高鍋 本番当日
2011年2月13日 07:00
 | |
| 今日は、これから、『夢を語ろう! トークライブin高鍋』です。 約800枚の前売り券が売れました。 今日何人の方が会場に足を運んで下さるか、楽しみです。 会場を熱い思いのこもった熱気でいっぱいにしたいと 思います。 実行委員は、9:00に会場集合です。 午前中に準備をして、12:30会場、13:00開演です。 打ち上げまで入れて、半日を超える長丁場、思いっきり、 精一杯、みなさんの予想を上回れるように、顔晴ってきます。 今日は、以上です。 |
夢を語ろう! トークライブ in 高鍋
2011年2月12日 08:00
いよいよ、中村文昭さんと大嶋啓介さんによる、トークライブin高鍋の開催が明日に迫りました。 ワクワク・ドキドキが高まってきます。
1か月という短い時間でしたが、実行委員一人一人が精一杯動き、準備をし、お声かけをし、ここまで来ました。 実行委員の皆さんの熱い思いが、あす来場して頂いた方々に伝わることを願いながら、最後まで、準備をしていきたいと思います。
中村文昭さんのメールにも、取り上げて頂きました。 以下に添付をします。
みなさまこんにちは。
なんだか…ものすごく寒い!!っていう時期は過ぎてしまいましたでしょうか。
今年の冬は寒いぞ~と気合を入れてたのに、
2月に入ってからちょっと暖かくなりましたかね。
さて、天気の話はもういいとして
今日は、今日本で一番大変な地域と言っても過言ではない
宮崎県の講演会のお知らせです。
友人に様子を聞くと、ニュースで流れるよりも現場はもっと深刻なようです。
新燃岳の噴火により、交通も農業も多大なダメージを負っているようです。
なんだか…ものすごく寒い!!っていう時期は過ぎてしまいましたでしょうか。
今年の冬は寒いぞ~と気合を入れてたのに、
2月に入ってからちょっと暖かくなりましたかね。
さて、天気の話はもういいとして
今日は、今日本で一番大変な地域と言っても過言ではない
宮崎県の講演会のお知らせです。
友人に様子を聞くと、ニュースで流れるよりも現場はもっと深刻なようです。
新燃岳の噴火により、交通も農業も多大なダメージを負っているようです。
しかし、宮崎の人たちは強い!
こんなときこそ隣人同士が協力し合い、
支え愛の精神が必要になってくるときかと思います。
2月13日は大嶋啓介君とのコラボイベントです。
僕らにどれだけのことができるかは分かりませんが、
宮崎の皆さんのため精一杯のことをやらせていただこうと思います。
以下詳細と主催者さんの思いです。
↓
===========================
今、宮崎はまた新たな試練に直面しています。
口蹄疫からの復興に進み始めた矢先、鳥インフルエンザが拡大しています。
加えて、新燃岳の噴火が起こり、甚大な被害を及ぼしています。
未だ、口蹄疫のダメージから立ち直っていませんが、
人が動かない事、お金が動かない事により、経済の循環がストップしてしまう事
が、いかに地域の活力を奪ってしまうのか、ということを口蹄疫の時に経験しました。
こういう環境のなか、私たちは立ち止まってしまうことなく、自分達のできることを
実行していくしかないのかなと思っています。
2月13日(日)に中村さんと大嶋さんの講演会を企画し、呼びかけをしてきましたが、
今年に入ってすぐ、児湯地区で鳥インフルエンザが発生し、思うように人が集まっていません。
宮崎県の見解では、鳥インフルエンザは飛沫感染はせず、人が媒介するものではないので、
イベントを自粛する必要はない、防疫を十分にし(足元の消毒だけで十分)、
農場への立ち入りの禁止等の告知を行ってから開催する事、とのことです。
口蹄疫に引き続き、鳥インフルエンザでダメージを受けている児湯地区での開催です。
地元の方々と一緒に、困難に負けない気持ち、明るく未来を描く気持ち、について考えたいと思っています。
季節柄、大変お忙しいかとは存じますが、お知り合いの方もお誘いの上、ご参加いただけますと幸いです。
=========================
こんなときこそ
助け愛、励まし愛、支え愛!
こんなときこそ隣人同士が協力し合い、
支え愛の精神が必要になってくるときかと思います。
2月13日は大嶋啓介君とのコラボイベントです。
僕らにどれだけのことができるかは分かりませんが、
宮崎の皆さんのため精一杯のことをやらせていただこうと思います。
以下詳細と主催者さんの思いです。
↓
===========================
今、宮崎はまた新たな試練に直面しています。
口蹄疫からの復興に進み始めた矢先、鳥インフルエンザが拡大しています。
加えて、新燃岳の噴火が起こり、甚大な被害を及ぼしています。
未だ、口蹄疫のダメージから立ち直っていませんが、
人が動かない事、お金が動かない事により、経済の循環がストップしてしまう事
が、いかに地域の活力を奪ってしまうのか、ということを口蹄疫の時に経験しました。
こういう環境のなか、私たちは立ち止まってしまうことなく、自分達のできることを
実行していくしかないのかなと思っています。
2月13日(日)に中村さんと大嶋さんの講演会を企画し、呼びかけをしてきましたが、
今年に入ってすぐ、児湯地区で鳥インフルエンザが発生し、思うように人が集まっていません。
宮崎県の見解では、鳥インフルエンザは飛沫感染はせず、人が媒介するものではないので、
イベントを自粛する必要はない、防疫を十分にし(足元の消毒だけで十分)、
農場への立ち入りの禁止等の告知を行ってから開催する事、とのことです。
口蹄疫に引き続き、鳥インフルエンザでダメージを受けている児湯地区での開催です。
地元の方々と一緒に、困難に負けない気持ち、明るく未来を描く気持ち、について考えたいと思っています。
季節柄、大変お忙しいかとは存じますが、お知り合いの方もお誘いの上、ご参加いただけますと幸いです。
=========================
こんなときこそ
助け愛、励まし愛、支え愛!
以上です。
採用活動/選考会
2011年2月11日 07:00
会社単独の説明会を行ったあとは、選考会へ移ります。
選考会は、段階的に1次、2次、最終と進みます。それぞれの選考会で何を行うかは、お楽しみです。
しかし、型どおりの一般教養筆記試験や面接試験は行いません。 楽しみながら、グループワークをして頂きます。
何を知っているか? 何ができるか?よりも、日頃から、何を考え、何を行っているか、ということの方が大切だと思います。 その時だけの受験対策・面接対策をして試験に臨んでも、意味がありません。 真剣に何のために働き、何のために生きるのかを考えている人の方が、人間力が勝っていると思います。
最近、人前でお話をする機会を頂くと、大嶋啓介さんの“本気のじゃんけん”をTTP(徹底的にパクル)しています。 自分は、いざという時はいつでも力を出せるから、と、日頃、力の出し惜しみをしている人ほど、いざという時には、自分の持てる力の半分も出せないと思います。 日頃から、力を出し切るつもりで動いていなくては、本当に力が出なくなってしまいます。 だから、思いっきり自分を出してみたら?と話をします。
大嶋さんが、講演でよくノミの実験の話をします。 ノミは通常2mの高さまでジャンプをする。 そのノミをコップに入れふたをすると、初めはふたにぶつかりながらトライを続けている。 しかし、何回もぶつかる内に諦めてしまい、ふたを外してもコップから飛び出すまでのジャンプする事ができなくなる、という話です。
ノミと同じで、人は大きな可能性を秘めているのに存在なのに、自分の限界を自分の思い込みで決めてしまう事がある、という教訓だ、と私は受け取りました。
どんなときも、全力でチャレンジしているとおのずから自分の壁を打ち破り、可能性を無限に広げていけると思います。 まわりの目を気にしたり、自分の限界を自分で決めてしまう事はとってももったいない事です。
面接のテクニックを磨くよりも、日頃の自分を出して、自分の考え方や思いを思い切りぶつけて、自分の可能性を信じてほしい、と訴えた方がいいのになあ、と思いつつ採用活動をしています。
以上
県北企業説明会 in 延岡工業高校
2011年2月10日 07:00
2月15日に延岡工業高校で、県北企業説明会が行われます。
宮崎県工業会県北地区部会と延岡市工業振興課、延岡工業高校&日向工業高校の主催です。
地元高校の生徒さんに対して、働く事の意味を考えてもらうと共に、地元の企業を多く知ってもらおうという企画です。 産業界と学校と行政が一緒になって、地域の産業教育を考え、連携する活動の一環です。
先日は、延岡工業高校でその事前打ち合わせ会議が行われました。 大変忙しい業務の合間を縫って、14社もの企業さんに集まって頂きました。
何といっても、延岡工業高校の富山校長先生の熱意が素晴らしい。 昨年までは、12社程度の参加企業数でしたが、ことしは、30社は参加して欲しいと、学校側から要請を受け、参加企業を集めるのに、苦労をしているところです。 地元の企業の方々には、直接学生さんと触れ合う良い機会ですから、多数参加して頂きたいところです。 企業側から一方的にプレゼンテーションをするのではなく、学生さんが何を考え、企業側からの話をどう受け止めるのか? 交流する良い機会だと思います。
この打ち合わせに合わせて、学校内の設備を企業にも見てもらう機会を設けていました。 生徒さんの作った作品、コンピューター、工作機械、実験装置、等々、見せて頂きながら、学習する内容の話を聞かせて頂きました。
ものづくりもやはり人です。人材育成なしには、いい物は作れません。産業界と学校が一体となって、ひとづくりをしていくことが大切だと改めて感じました。
以上
こころざし課題図書(平成22年2月度)
2011年2月 9日 06:30
“こころざし”平成22年2月分課題レポートは、始めませんか「弁当の日」 / 鎌田實、竹下和男 でした。 その時に提出した私のレポートを以下に掲載します。
1.読後感
水永さんからの最後の課題図書を読み終えて、本書に水永さんからのメッセージが込められているような気がしました。まず、社会との関わり合いを大事にし、「自分にできる何か」を探し、行動を始めなさい、ということ。次に、共感する力や創造する力、気づく力をつけて、豊かな人生を送りなさい、ということ。現代は、個人の欲望を刺激することによって成り立つ、行き過ぎた個人主義や金融資本主義によって、社会とのかかわりが薄れてきている気がします。その事への問題提起が本書に含まれていると思います。
先日延岡で行われたロボットシンポジウムで基調講演をされた、千葉工業大学の古田所長が次のようにおっしゃっていました。「これからのロボット産業はサービス分野に目を向けなくてはいけない。地域の課題を解決することにロボット技術が活用できる。ロボットはモジュール化が進み、誰でもできるようになる。ロボット技術を使って何をするのかが重要だ。問題を多くかかえている地方の方が、発想が生まれやすい。延岡ならでは物を考えるべきだ。」
自分の頭で考え、自ら気づき、自分の力で行動を始めることが、これからのビジネスに必要なことだということを、弁当の日を通じて、それを教えられました。
2.空気を読み過ぎるな、空気を作りだせ。
空気を読めない、という言葉があまり好きではありません。居心地良い空気を作って、みんなと横並びで、仲良くすることはいいことかもしれません。しかし、みんながあまりにも空気を読み過ぎると、建設的な事が生まれないような気がします。
竹下さんは、10年間の校長職の間、「私が前例になる」という構えを通してきた、とおっしゃっています。社会に適応するために必要な物を身につけている「社会性」は、非常に大事ですが、社会そのものを変えていく力「社会力」が、今もっと重要になってきていると思います。自分の価値観や思いをしっかり主張するとともに、駄目なことをダメといえる事が大事だと思います。
価値観の多様化とか、個人の権利の主張が全面にで過ぎたために、逆に社会の事を自分の事として考えて、ものをいう人が減ったような気がします。空気を読むということが、自分の保身のみを考えることとつながらなければいいが、と思います。
大量生産された“もの”を買って、満足する社会から、自分で考え、自分で作りだすことに喜びを感じる社会に変革していく必要がありそうです。私達中小企業も、大企業から頂く仕事を待っているのではなく、社会の課題を解決するために自ら考え、自らの力で一から作りださなくては、生き残っていけない時代が来ているのかもしれません。
3.地域とつながる、家庭とつながる。
“弁当の日”は、家庭教育と学校教育を重ねる手法だ、親と教師が連携する対策だ、という言葉が出てきます。家庭・学校・社会・会社を切り離して考えることはできないという事を教えられました。
それぞれを切り離して考えるところから“気付く力”をなくしていっているような気がします。“思いやる力”“想像力”をなくしているような気がします。そして、“働く”ということの意味や意義を理解しなくなってきていると思います。働く姿を見せること、一生懸命生きる姿を見せること、が大事だと思いました。
地域とつながり、地域の課題を見つけ、解決するビジネスモデルを作ること、家庭とつながり、子供を育て、気づく力を育て、社員の豊かな人生を作ること、これらのことが、我が社のこれからの課題です。
私達、中小企業経営者は、もっと地域とつながりを持たなくてはいけないと思います。儲け3割、仕事7割。 地域が良くならなければ、人が育たない、会社も発展しない。
以上



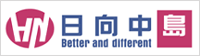

最近のコメント