鹿児島銀行 日向経友会 舞の海さんの講演
2011年2月 3日 07:30
先日、鹿児島銀行の日向経友会で、舞の海秀平さんの講演を聴く機会がありました。
年間80講演ほど行っているとのこと。 とってもお話が上手で、飽きさせず数々のエピソードやご自身の相撲への思いを話して頂きました。 特に頭にシリコンを入れたくだりは、その必死さが目に浮かぶようでした。
相撲は勝負事である前に、伝統文化であり、神事である。 神様の前で勝負事の奉納をしている。 だから、作法が大事なんだというお話しでした。
グローバル化の波にのみこまれて、外国人力士が増えたことにより、良き伝統も無くなりつつあるというお話には、非常に残念な気持ちになりました。
そして、今、多くの不祥事が取りざたされています。 野球賭博問題から八百長疑惑まで、相撲界の屋台骨を揺るがす問題となってきています。 これも現在の日本の社会が抱える問題と根っこは同じかもしれません。 まず一つは、倫理観や道徳観、考え方や価値観に関する教育なしに、個人の権利や自由を主張する社会となってきているということ。 そして、これまで長く閉鎖的でなれ合いの関係性の中で回っていた社会が、透明性と要求されるようになってきたということ、だと思います。
中傷や批判をするばかりでなく、あるべき姿を建設的に話し合い、変化していくことをサポートするようになれればいいのに、と思います。 この社会はつながっていますし、自分達が作ってきた社会なのだから、誰かを批判したり、責めたりしても、問題は解決しないと思います。
舞の海さんのお話の中に、参考になる話もたくさんありました。
「勝ってもおごるな、負けてもひがむな。」、「自信が過信・慢心、油断につながる。」、「自分の強みを相手の弱みにぶつける」 相撲界には、日本の伝統様式を守り、人を育てるなどの良い部分もたくさんあるはずです。
マスコミや政治家も、日本の伝統の良さを活かし、育てることも考えながら、発言をして欲しいなあと思います。
今日は節分です。季節感を感じさせる伝統行事も大切にしたいですね。
以上
こころざし課題図書(平成21年11月度)
2011年2月 2日 07:00
“こころざし”平成21年11月分課題レポートは、成功は一日で捨て去れ / 柳井 正 著でした。 その時に提出した私のレポートを以下に掲載します。
1.読後感
読後の率直な感想は、柳井社長が経営者としての高い志と能力を持った方だということだ。ドラッカーを師と仰ぐ通りに経営の王道をまっすぐに歩んでいるというように感じた。柳井さんが“大企業病”の兆候を自社に対して感じ、「第2創業」をテーマに社内の改革に挑戦した経緯、ベースにある「正常な危機感」を本全体と通じて感じた。それが無ければ、現状否定、継続した改革は生まれない。会社の規模は違えども、私が弊社に入社した10年前に、自社に対して感じたものと同じだった。
さらに、大きな志を抱いて挑戦をする「開拓者精神」を持ち続けている事をすばらしいと感じた。人口減少・収縮マーケットの日本経済の中で、閉そく感と停滞感に縮こまることなく、絶え間なく改革を続け、世界に挑戦する経営姿勢に大きな刺激を受けた。
資源や食糧、エネルギーを輸入に頼る国・日本が、将来にわたって飯を食っていくためには、技術開発、ビジネスモデルの構築など、世界に先駆けて新しいものを生み出していくところに優位性を見出していくしかないと思う。まさに柳井社長は、高い志を持って、開拓者精神で、世界に向けて挑戦を続けていると思う。
2.“ユニクロ栄えて国滅ぶ”を読んで
浜さんの論文は、よくわからない点があった。「安売り競争が企業の利益縮小、リストラ、賃下げ、さらなる値下げの悪循環を生む元凶である。『自分さえよければ病』という資本主義の原理が、経済のグル―バル化で加速した。しかし、保護主義と統制経済は非効率的な経済を生み出し、競争原理が働かない社会を作り出してしまう。」と言っている。浜さんが、「健全な市場経済」をどういうものと考えているのかが見えなかった。
企業は、より効率的に生産し、流通させ、販売する事を競い合っている。グローバル化して、世界規模での生産・流通・販売の仕組が可能になって、地域や業界の非効率性は見直さざる負えなくなってきている。もちろん、仕組みの変革を伴うことなく、利益を度外視した価格競争は論外だ。しかし、品質・コスト・デリバリーで競争をすることが、イノベーションを生み出すのではないだろうか。
一方で、大量生産大量消費の経済構造からは脱しなくてはいけないと思う。金だけが尺度の価値観から新しい価値観への転換期だと思う。ある映画の中で、ヨーロッパが自然エネルギーへ急速にシフトしている理由を次の様に説明していた。「ヨーロッパは100年後のあるべき姿から、現在の自分たちを見ることができる。そして、50年後、10年後にどこまで達していなくてはいけないか?だから、今自分たちが何をすべきなのか?という風に考えている。」
物をたくさん持って、たくさん消費すれば幸せだった時代を経験し、「本当の幸せとは何なのか?」について、考えられるときが来たのではないか?物質的にも精神的にも豊かな人間社会を送るために持つべき価値観を考えて行きたいと思う。
3.目指す経営者像
将来を見通すことはできない。経済環境の予測をすることも容易ではない。しかし、だからこそ、経営者として必要なことは、「こうありたい、こうあるべき」という将来像を描き、従業員に明快なメッセージを送ることではないだろうか?ユニクロの“新年の抱負”には、柳井社長の強いメッセージが込められている。ビジョンを明確にし、ビジョン実現のために必要な要素を的確に従業員に明示することを見習いたいと思う。
そして挑戦する気持ちを持続けたい。
以上
会社の安定・継続と、挑戦・改革を共に求めるのは難しいように感じます。 常に変化・改革をしていくことが、継続につながり、外から見ると安定しているように見えるのかもしれません。 環境が常に変化をしている中で、自社だけが変わらないまま、存在し続ける事はあり得ません。
いつも破壊と創造をするように努めて行きたいと思います。
以上
社員への手紙 その22
2011年2月 1日 05:08
今回は、平成15年7月1日に書いた7月度の手紙です。
拝啓
まだしばらくの間、雨が降ったりやんだりの日が続きそうです。雨にぬれたり、部屋の除湿で室温が下がりすぎ、体調を崩すことも多くなる季節です。お身体には十分お気をつけください。
新しい月が始まりました。繰り返しお話をしていますが、我が社にとっては大変重要な3ヶ月になります。この3ヶ月を協力して乗り切っていきましょう。
先日、政治評論家の森田実さんの話を聞きました。
今の状態は、異常である。一年以内で振り子は元に戻る。消費を拡大し、成長政策をとる政権に変わり、景気も今の状態を脱する。という話をしていました。
明るい未来を信じて、できることを精一杯実行していく。全員で一致団結して、安心して働ける環境を作っていくこと。が大事だと改めて感じました。
もし景気が戻っていくとしても、今私たちができることをやり、改善をすすめ競争力をつけておかなければ、我が社の成長はないと思います。
先日の打合せの際に全員から出してもらった行動目標(提案)からこの3ヶ月に実行していくことを要約しました。本日から具体的に実行していきましょう。
営業は、①4人が連携して、先行して売上げ見込みを管理し、受注量を確保していく。 ②実行予算を組み、製造の目標をたてる。 ③受注票や注文票など必要な手続きを確実におこなう。
製造は、①工数を目標数値に納めるよう協力して効率的に作業をする。 ②工事の内容を一人ひとりが把握し、全員が無駄なく、動けるようにする。 ③工具の管理をしっかり行う。 ④消耗品の無駄遣いをなくす。
設計は、初期打合せを密にして、製作図の手直しを少なくする。
皆さんが日頃から考えていることですし、みんなが納得し、意識して行動すれば、難しいことではありません.
いつも、実行していく際に、考え方や性格の違いが問題となります。全員考え方が違いますし、自分に自信とプライドを持っています。それは大事にして行きたいと思います。しかし、全体の目標を達成するために障害となる悪い習慣や癖は改めていかなくてはいけません。
毎日の生活の中で、何か一つ変えてみる。それだけで、自分の習慣が変わる、見えていた世界が変わることがあります。難しいことは出来ないと、考えるのではなく。まずできることから、少しずつ実践してみましょう。
毎日、毎月、毎年、すこしづつ進歩し、発展していく自分であり、会社でありたいものです。
敬具
脳科学者の茂木健一郎氏は、次のようにいっています。
『人間の脳は、楽観的でなければその潜在能力を発揮できない。』
できない理由や言い訳を考えるよりも、明るい未来を信じ、自分を信じ、まず動いてみることが、もっとも大事なことだと思います。
以上



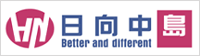

最近のコメント